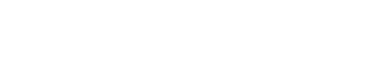「はっけよいのこった!」――相撲の取り組みでおなじみのこの掛け声、実はとても深い意味を持っていることをご存じですか?
江戸時代から続くこのフレーズには、力士を鼓舞し、勝負の流れを作る役割があります。
また、相撲は単なるスポーツではなく、日本の伝統や神事と深く結びついた文化でもあります。
本記事では、「はっけよいのこった」の由来や語源、相撲の歴史、さらには相撲の未来について詳しく解説!
相撲の魅力をもっと深く知り、楽しむためのポイントも紹介しますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
「はっけよいのこった」の由来と語源
相撲の取り組み中に行司が発する「はっけよいのこった」。
この掛け声には、長い歴史と興味深い語源があります。
①「はっけよい」の語源とは?
「はっけよい」の由来には、いくつかの説があります。
🔹 八卦(はっけ)説
「はっけよい」は漢字で「八卦良い」と書く説があります。
八卦とは、中国の易経(えききょう)に登場する占いの方法のこと。
この言葉が「勝負の流れが良い」「相撲の展開がスムーズである」という意味で使われるようになったという説です。
🔹 発気揚々(はっきようよう)説
「はっけよい」は、「発気揚々(はっきようよう)」が変化したものとも言われています。
発気揚々とは、「気力が充実して勢いがある」という意味の言葉。
この言葉が縮まって「はっけよい」になり、力士の闘志を鼓舞する掛け声になったと考えられています。
🔹 「早くせよ」説
他にも、「早くせよ(はやくせよ)」という言葉がなまって「はっけよい」になったという説もあります。
相撲は攻める競技なので、行司が「早く動け!」と催促する意味で使った可能性もあるのです。
②「のこった」の意味とは?
「のこった」は、相撲独特の言葉ですが、意味はとてもシンプルです。
土俵の上で力士が相手の押しや技に耐えて、まだ倒れていない・土俵の外に出ていない状態を指します。
行司が「のこった、のこった!」と繰り返すのは、「まだ勝負は続いているぞ!頑張れ!」という意味合いがあるんですね。
③ 江戸時代から続く伝統の掛け声
「はっけよいのこった」は、江戸時代にはすでに相撲の取り組みで使われていた記録があります。
行司が掛け声を出すことで、勝負の勢いをつけ、観客の盛り上がりを引き出す効果もあるのです。
現代でも、大相撲の土俵上で行司が力士の動きを見守りながら「はっけよいのこった!」と声をかけるのは、相撲の見どころのひとつになっています。
「はっけよいのこった」はどんな場面で使われる?
行司が「はっけよいのこった!」と声をかけるのは、力士同士が組み合い、勝負が決していないときです。
特に、がっぷり四つに組んで動きが止まってしまったときに、「もっと動け!」と促す意味で発せられます。
逆に、一方の力士が一瞬で勝負を決めると、掛け声をかける暇もなく勝敗が決まることもあります。
まとめ
「はっけよいのこった」は、相撲の取り組みを盛り上げる伝統的な掛け声であり、江戸時代から現代まで受け継がれてきました。
この掛け声には、「もっと動け!」という意味が込められており、力士たちを鼓舞する役割を持っています。
また、相撲は単なる格闘技ではなく、神事としての側面も持ち、日本の文化と深く結びついています。
近年では、女子相撲の発展やeスポーツ化、国際化が進み、相撲の新しい楽しみ方も広がりつつあります。
これからも「はっけよいのこった!」の掛け声とともに、相撲の伝統が未来へと受け継がれていくことでしょう。
次に相撲を観るときは、ぜひ「はっけよいのこった!」の掛け声にも注目して、その魅力を存分に味わってくださいね!