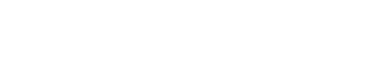「どうして人はルールを守るのか?」
この疑問に答えるのが、アメリカの社会学者トラヴィス・ハーシが提唱した**ソーシャルボンド理論(Social Bond Theory)**です。
この理論では、「人は社会とのつながりがあるからこそ、犯罪や非行をしない」と考えます。
もし社会とのつながりが弱まると、ルールを破るハードルが下がってしまうのです。
この記事では、ソーシャルボンド理論の基本概念や4つの要素(愛着・投資・関与・信念)を大学生にもわかりやすく解説します。
さらに、この理論がどのように社会で応用されているのかについても紹介するので、ぜひ最後まで読んでみてください!
ソーシャルボンド理論とは?
ソーシャルボンド理論は、「人は本来、ルールを破りやすい存在である」という前提に立っています。
しかし、多くの人が犯罪をしないのは、社会とのつながり(ソーシャルボンド)が強いためです。
もし、このつながりが弱くなると、「ルールを破ってもいいや」と思うようになり、非行や犯罪につながる可能性が高まります。
ハーシは、この社会とのつながりを4つの要素に分けて説明しました。
ルールを守る4つの要素
① 愛着(Attachment) ~大切な人を失望させたくない~
人は、家族や友人、恋人、先生など身近な人とのつながりを大切にします。
「親に迷惑をかけたくない」「先生に失望されたくない」といった気持ちがあると、自然とルールを守るようになります。
この「愛着」が強いほど、逸脱行動を抑える効果が高くなります。
例:
- 家族や恋人に心配をかけたくないから、夜遊びを控える
- 教授やゼミの仲間に悪い印象を持たれたくないから、真面目にレポートを書く
② 投資(Commitment) ~今までの努力をムダにしたくない~
「今まで積み上げてきたものを失いたくない」という気持ちも、ルールを守る動機になります。
例えば、大学での成績、就職活動、スポーツやバイトでの実績など、時間をかけて築いたものがあると、「これを台無しにしたくない!」と思いますよね。
だからこそ、大きなリスクを伴うような行動(犯罪や不正)を避けるようになるのです。
例:
- 内定が決まったのに、万引きをして前科がついたらすべて台無し
- 単位を落としたら、これまでの努力が無駄になるから、カンニングはしない
③ 関与(Involvement) ~忙しくて悪いことをする時間がない~
人は、部活、バイト、勉強、サークル活動など何かに熱中していると、犯罪をする時間がなくなるものです。
「暇を持て余している人ほど、悪いことをしやすい」というのは、意外と真理なのかもしれません。
例:
- 週5でバイトしていたら、夜遊びや飲み過ぎる時間がない
- ゼミの研究が忙しくて、くだらない悪ふざけをする余裕がない
④ 信念(Belief) ~ルールは守るべきもの~
「ルールは守るのが当たり前」「法律は破ってはいけない」という価値観や信念を持つことも、犯罪抑止につながります。
もし、「別に法律なんて守らなくてもいい」「バレなきゃ何をしてもいい」という考えの人が増えたら、社会全体が混乱してしまいますよね。
このように、道徳的な価値観が強いほど、犯罪や不正をしにくくなるのです。
例:
- 「人を傷つけるのはよくない」という価値観があるから、暴力をふるわない
- 「カンニングはズルだ」と思うから、テストで不正をしない
ソーシャルボンド理論の応用
この理論は、犯罪学や社会学だけでなく、教育や心理学の分野でも活用されています。
たとえば、青少年の非行を防ぐためには、以下のような取り組みが有効です。
✅ 家庭での愛着を強める
- 家族と会話する時間を増やす
- 親子の信頼関係を深める
✅ 社会的な投資を促す
- 進学や就職の目標を持たせる
- 自分の将来について考える機会を増やす
✅ 関与の機会を増やす
- 部活動やサークル活動を推奨する
- アルバイトやボランティアの機会を増やす
✅ 正しい信念を育てる
- 倫理や道徳を学ぶ機会を作る
- 「ルールを守ることの大切さ」を伝える